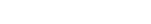満を持してスタートした
新学科、
クリエイティブ
イノベーション学科。
その展望と
美大の目指す未来
武蔵野美術大学
クリエイティブ
イノベーション学科
主任教授 井口 博美氏
トーリン美術予備校
学長 瀬尾 治
学長補佐 佐々木 庸浩
武蔵野美術大学は2019年4月に造形構想学部クリエイティブイノベーション学科と大学院造形構想研究科クリエイティブリーダーシップコースを新設し、新たに市ヶ谷キャンパスを開設しました。小平市の鷹の台キャンパスでは学部1年生が、同時開設された市ヶ谷キャンパスでは大学院生の一期生が新しい学びを始めています。どんな学生が新学科に集い、どんな教育が展開されているのか。井口博美教授に話を伺いました。
- クリエイティブイノベーション学科(以下、CI) が開設されて1年が経とうとしています。
-
開設準備の段階から、ムサビが長年培ってきた造形教育を「創造的思考力」を養うために応用するというCIのコンセプトを、どれだけ社会に認識してもらえるかの勝負だったと思います。
もともと新学部・学科設立の背景には、アートやデザインに対するニーズが社会的に高まり、総合大学でもデザイン系学部・学科の設置が増える中で、美大はこのまま静観していて良いのかという思いがありました。
武蔵野美術大学の教育の本質は、クリエイティブなスキルの伝授だけでなく、主体性、人間性、思考力、表現力を培う総合的な人間形成を含めた造形教育にあります。
美大と聞くと、狭い意味でのアーティストやデザイナーを養成するところというイメージが一般的かもしれませんが、これからの時代を生き抜くうえでとても大切な人間力を培う場であることを、きちんと社会にプレゼンテーションする—— 保護者や高校の先生より、かえって高校生のほうが感覚的にこのことを理解してくれていると感じますね。
- CIは実技試験がなく、文系・理系を問わない学力のみの入試方式を取り入れています。従来の美大と異なる入り方で、一期生にはどんな学生が集まってきたのでしょうか。
-
もともとムサビは全国から学生が集まりますが、今まで美大進学を考えたこともなかったような層、たとえば総合大学の総合政策系の学部を志望していた学生がCIを選んでくることもあります。
両親がデザイナーで子どもの大学選びにあたってCIを知り、「こんな学科があるなら自分が入りたかった」というふうに、親から勧められたという学生や、保護者や高校の先生に反対されて美大受験を一度は諦めたけれど、進学相談会やオープンキャンパスに親を連れてきて説得した学生もいる。一期生として入学した80名は、それぞれのハードルを越えてきていると思いますね。
ただ、私自身が学生に望んでいるのは、CIに目を向けるきっかけが親の勧めや広告だったとしても、最終的には自分自身で覚悟を決めて入学してほしいということです。合格した中で一番偏差値の高いところを選ぶなんてことではこれからは通用しないし、デザインといっても総合大学のデザイン系学部・学科とは異なる特色があります。
-

CI の1 期生はもともと総合大学を志願していたような層が集まった
写真左より:井口博美教授、佐々木庸浩、瀬尾治 - 覚悟、とはどんなことでしょうか。
-
CIの教育内容と合わせて説明すると、教養科目や造形実習・演習に加えて、情報を順序立てて伝える能力と現代社会を長い時間軸で捉える能力という二つの軸で「創造的思考力」を養っていく2年間なんですね。
特に造形教育については、絵を描いたことがないという前提でカリキュラムを組んでいますから、デッサンや塑造といった造形の基礎を学ぶ「造形実習」と、デザインリテラシーやエディトリアルデザインなどを学ぶ「造形演習」が、月曜日から金曜日まで、丸2年続くわけです。
これは、相当な覚悟がないと乗り越えられない。モチーフを観察するといっても、じっと座っているだけでは何を描けばいいのかわからない。そうやって苦しみながら自分自身で答えを見出していかないと、造形の本質をつかむことはできないし、こちらが与えたいと考えている造形の基礎力も身に付きません。
でも、入学して2、3カ月経った学生と話すと、「デッサンが描く力ではなく観察力が重要だとわかってきた」なんて言葉が本人の内側から出てくるようになる。それは、座学で何百時間、アートやデザインを学んでも得られない、美大教育の真骨頂だと思います。
また、CIは新しい造形構想学部の学科ではあるものの、造形教育は日本画学科、油絵学科、彫刻学科と造形学部の教員が総動員で、従来の造形教育と同じプログラムを展開しています。受験のために準備したスキルがない分、純粋で教え甲斐があるという話も教員から聞いていますし、造形学部の各学科とCI、お互いにとっても新しい可能性を見出すきっかけになっていると感じます。
-

造形実習I の授業風景。造形の基礎を学び対象を観察する力や自らの手で表現する力を養う - 学生の雰囲気は、造形学部の学生と何か違いを感じられますか。
-
美大はどの学科も女子の比率が高いのですが、CIは比較的男子の割合が高いですね。また、クラス委員長や生徒会長をやっていたり、地域のコンクールで賞を獲っていたりと、地域のリーダー役だったような学生も多く集まっています。
ただ、それが裏目に出るときもあって、「課題探求」という授業のグループワークを入学後すぐ行うのですが、今までリーダーをやってきたような人ばかり集まっているから、みんな引かない(笑)。課題の目的や意図についても教員がロジカルに説明しないと彼らは納得しません。時には手を焼きますが、良い意味で手応えを感じています。
加えて、自分たちで勉強することにも慣れていると思います。興味を持ったテーマは「参考になる本を教えてほしい」と相談に来るし、図書館や書店等で本を探してきて仲間を募って、読書会を開いて議論するなんて光景は、今までの美大ではなかなか見られませんでした。サークルに入っている学生の比率も高いですね。
-

造形教育で培われる創造的思考力を生かすため、
基礎課程では現代社会や産業を含めた幅広い教養教育も展開するほか、
3・4 年次からの専門課程の土台となる実習や概論を通して、
各自が追究したい専門領域を見出していく - 一期生は1年後、3年次になると市ヶ谷キャンパスでの学びも始まります。
-
鷹の台キャンパスで「創造的思考力」の基礎となる造形力や教養を身につけたうえで、市ヶ谷では世の中の動きとリンクしながら、「創造的思考力」を社会で応用する方法を、プロジェクトベースで実践的に学んでいきます。
大学院(造形構想研究科クリエイティブリーダーシップコース)と一体の教育も予定していますから、どんなふうに彼らが成長していくかはこちらも楽しみです。
-

市ヶ谷キャンパス 1F MUJI com 市ヶ谷キャンパス店内 
鷹の台キャンパス 15 号館
学生インタビュー
クリエイティブイノベーション学科(CI)で学ぶ5人の学生に、C Iを受験したきっかけや、印象に残っていたり自分の力になったと感じる授業、今後のことについて話してもらいました。
- 2019年度 一般入学試験 センター5教科型
Tさん -
国立の理系大学を目指していましたが、技術と美術の中心くらいのことをやりたいと思っていたとき、駅でCI の広告を見て受験してみようと思いました。基礎課程が始まってまだ半年ですが、Illustrator の使い方からデザインや美術関連の知識まで、しっかり学ぶことができています。今後は個人的に活動しているダンスと美術を繋げたいと考えています。造形構想学部では他学部(造形学部)の各学科が開講している授業の一部も履修できるので、積極的に利用していきたいです。
- 2019年度 総合入学試験 数学力重視型
Mくん -
認知神経科学分野への進学を考えていたとき、CIを知りました。より広い分野の勉強がしたかったし、もともと美術には興味があったので、入学後の絵画や彫塑の授業にはすごく満足しています。特に「造形実習Ⅰ(共通絵画)」では、実際に手を動かしたりアート系の先生と話をする中で、ものの見方がすごく変わりました。鷹の台キャンパスにはいろんな人が集まっていて、他学科の学生が 展示をしていたり、とても刺激がある環境ですね。
- 2019年度 総合入学試験 構想力重視方式
Oさん -
コトのデザインに興味があり、経営やマーケティングとアート、どちらの領域も学びたいと思っていたので、唯一それを叶えられるCI を志望しました。夏休みに自画像を描く自由課題があったのですが、その課題を機会に他者との距離感や空間を自分で言語化できたことで、自己効力感が高まったと感じています。作業や講評の場で、先生に批評してもらうことで自分の中に伸びしろがあるなと思えるし、ときには厳しいコメントも自分の成長に繋がると感じています。
- 2019年度 指定校推薦
Kさん -
ムサビのデザイン情報学科やタマビの統合デザイン学科が志望学科でしたが、デザインをバリバリやるというよりは企画を出す側のほうが好きだったことや、高校のときにみんなでアイデアを出し合ってモノをつくった経験から、「創造的思考力」の楽しさと必要性を感じて、CI を受験しようと思いました。「災害とデザイン」に興味があるので、これからもその学びを深めながら、他大学の友人と共同制作ができないかなと思っています。
- 外国人留学生 特別入学試験
Sくん -
韓国からの留学生です。美大志望から文系に方向を変えて受験勉強をしていたところ、友達の紹介で偶然この学科を知って受験を決めました。楽しかった授業は「造形実習Ⅱ(共通彫塑)」。合宿みたいな雰囲気で、彫塑をやっている間に人間関係も築けました。入学前のガイダンスで、教授たちが「市ヶ谷キャンパスはみんなで作っていくキャンパスです」と言っていたのが印象的です。都心のキャンパスだからこそできることがあるんじゃないかと楽しみにしています。
インタビューはクリエイティブイノベーション学科(CI) の学科サイトで公開中の座談会を再編集したものです。全編は下記のバナーよりご覧ください